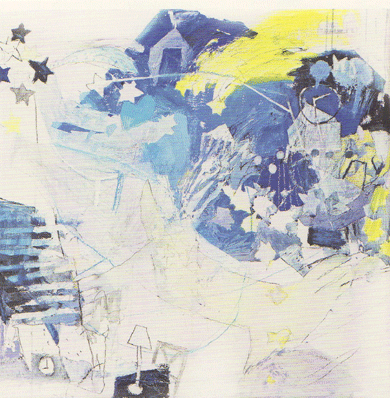
中村眞弥子さんの、絵の中身と、同じような形象を自分のなかに探すと、小さい頃の落書きの世界にすなおに跳んでゆけるような気がする。
恐らく、誰もがそうであろうが、落書きは、私達の中にある遠い過去の部屋の奥に、すでにしまわれているようなものだ。
そこで、自分の落書きの経験というものを思い出しながら、改めてこれら中村さんの絵を眺めてみると、落書きというのが、一つの世界であった、という印象がますます強まる。
例えば、落書きは、どうして重力の法則からはこんなに自由に遊離してしまえるのだろうか。
見知らぬ界域に舞い降りたら、そこでは「自然・物理」の法則が役にたたなかった・・・。
それは、私達の心の内部へとむかっているのだ、と語るにしても、幼い頃の、あの自由さに届くには、ある方法でこの現実の自然社会から遠い場所へと脱出してみなければならない。
緑の葉っぱ、黄色のくだもの、赤い木の実・・・、
猫の眼の窓、鳥の羽根、夜と星、遠くの家、机上のスタンド・・・、
絵を観ていると、これらの名称がそこここに浮かびあがる。
それらは、私達の「ここ」という場所から脱出するに際しての「呪文」なのだといっても不思議は感じない。
落書きは常に、道ばたに描かれ、空地の地面に、白墨やロウセキで描かれた。
雨が降る日などを過ごしているうちに、それらは知らぬ間に、自ら消えるように姿を消した。
そうして、描き手が、成長する過程で、いつの間にかその世界との交流はとだえる。
今日、地下鉄に描かれ、歩道橋に描かれ、他人の商店のシャッターに描かれる、あの未だ孤独からの脱出口を見つけられないでいる、鬱屈の「ラクガキ」とは、幸いにして無縁の世界だ。
道ばた、とは何であったか?
空地の地面、とは何であったか?
「空」(そら)なのだという返事がどこからかきこえてくる。
それは、すぐに手が届く小枝たちがつくる空間であったり、遠く望まれた青い「空」であったりした。
その「空」を、自由に泳ぎ、遊んでいることができた。
この「空」がいつから「キャンバス」に相当するもの、に等しくなったのか、それは、本人にしかわからないことだろうが、中村眞弥子さんが、「絵を描こう」と思い、そして描き終えた時、どんな心的世界に跳んでいたのか、共鳴ほどの想像が、観る者にもうながされる。
先ずは、「空」という空間、それは具体的にはキャンバスに相当するものを意味するのだが、クレヨンや絵の具を抱え込んでいる背景の世界自体の「空」を、同時に生み出しながら描くことがこれらの絵の前提である。
彼女の素材は必ずしも「キャンバス」ではなく、石膏を利用したりして、特別な質感の「空」を作り出している。
自由な作画の主(あるじ)は、遊泳する「空」という空間を生み出しながら、その内側に遊泳する。
誰にとっても、それは懐かしさをともなった憧憬であろう。
