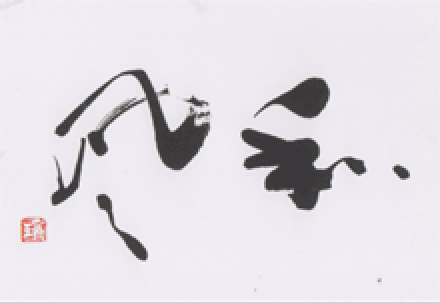1、菊池敬子さんの絵
どれくらい眺めていた景色であろうか?
どのような志向で眺めていたイメージであろうか?
それは、今しがた眠りから目覚めて、徐々に浮き上がるようにして訪れたのであろうか?
あるいは長時間見つめ続けた結果、突然のように観えたのであろうか?
それが、眼の外での出来事であろうと、眼の内部での出来事であろうとも、である。
いずれにせよ、どこからかやって来て、どこかへ行こうとしている時間がそこに流れている。
どこから、どこへゆく時間であるのか?
青い海から、青い面に、
群青色の空から、群青色の面に、
海の水平な彼方から、左右にのびる横線に・・・転じてゆく時間である。
それは、具体的な形から抽象へ転生するドラマなのだ。
頭の中に、点、線、面、が出現するという、脳裡における「事件」なのだ、ともいえる。
私が以下で、菊池春桂、敬子さん母娘の作品から連想するのは、
「線」というものの「認識」と、その「線」の「表出」についてである。
①「線」が脳裡に「出現」する過程を、敬子さんの絵から、
②そして、脳裡に生まれた「線」の「表現」を春桂さんの書から語り出したい、と考えている。

2、線が脳裡に出現するという巨大事件
菊池春桂さんと菊池敬子さんは、母娘である。
敬子さんは、親子の年齢の分だけ、母親の世界を先ずはリセットした所から制作を始めたということになるだろうか。
後に続いてくる人々は常に、宿命的にそのようにして現れる。
これは、ことばを変えれば新しく生まれてくるものが、個性の主体として出現するということである。
敬子さんの②の絵から、連想を開始しよう。
彼女は、スクリーンのような世界と共に眼を開いた。
この絵の画面から、時間を過去に遡ってみれば、光が明滅する現象のように、イメージが形成される以前の世界があったであろう。
恐らく眼が生まれた頃のことだ。
眼が生まれた頃とは、自己と世界が生まれたといえる頃という意味である。
その世界で、私達は、いづれ何を観ることになるのだろうか?
この画面から、時間を遡るのではなく、逆に時間を現在の方向へ進行してみると、眼からそのいくつかの点滅の映像が消える瞬間がやってきて、直接的な視覚世界の外に果てることになる。
そこで・・・何が起きるのだ!?
例えば、点滅がA点とB点の二つだと仮定すると、AとBの、二つの点滅を交互に見続けるのは、ここにある、二者(以上)の「関係」ということが把捉されようとしている。
そして、この二者(以上)の点滅を、その時、同時に捉えた!!
その瞬間、「関係」という認識がもたらされたのだ。
このことは、A・B(C・・・)という点たちを、同時に把捉し(得)たという世界に入り込むことができたと敷衍してよい。
それは、脳裡に「線」が出現したことを意味する。
*さらに、点・線・面の展開に、時間はそれほどかかるまい。
このことは、人の世界のうちで起きた巨大な事件だったといってよい。、
3、事情が変わった。
私たちが意識を集中させ、
見える部分的な世界を把握しようとした結果、
新たなイメージを獲得する、
そういう観る「技術」を高める鍛錬が続けられた。
その基礎鍛錬の日々が、人の幼少年期を襲っていたのだ。
二つ(以上)の対象を同時に捉えることを強いたのは、動物の自然な欲望からだが、そうして、「関係」を獲得するには、他の動物から自己を隔てるための、「無限」に比すべき時間が必要だったのだ。
それは認識としては「抽象」の世界が獲得されていったのだと考えてもよい。
「関係」・「抽象」という、知覚としては「見」えない世界を「観」ることになったのだ。
この意味で、人は、空、海、青・・・という直接的な知覚の眼を失う場所に飛躍することになった。
諸々の「関係」がこうして、私達の世界として出現した。
ここから、人は、後年抽象絵画を描く可能性を手にした。
私たちを取り巻く諸々の青や群青色や赤や黄色のイメージは、その背後に、見えない「関係」の存在を常に暗示することになった。
私達が、初期において、この抽象(化)の世界を獲得したからには、
認識上決定的な変化が生じた。
「線」を未だ知らなかった時に、海は果てしなく遠い青の彼方にぼんやりと霞んでいただけだったのだが、事情が変わった。
彼方に存る水平線、それが彼方に見えるのではなく、私達が「先ず線を頭の中に描くからこそ、海の彼方が水平線に見えるのだ。」というふうに認識の順序が変わった。
*以上のことは、「関係」というものを想う時、
知覚世界で、直接イメージ化することができない、
関係概念でしか問題にできない、という経緯をよく物語っている。
4、見えない関係を見える世界にもたらす。
海の茫洋とした彼方は、硯の上を泳ぐ墨の、液状の変幻と同じことだ。
筆が描いた文字が線に見えるとすれば、その線は脳裡において作られている。
形のない脳裡の線が、白い雪を墨色に染めるのは、その抽象が、墨という肉体をまとって、知覚の対象になり得なければならない・・・。
まさに、表現ということは、身体の内と外の世界を私達が総動員しているのだ。
敬子さんの母・菊池春桂(玲子)さんは、父親が書家であったから、ほんの少女の頃から「書」が身近にあった。
かの四国、松山に育った。
街を歩き、野に出でて香りを浴び、逍遥のうちに、風になびいている樹々に出会った。
幹や枝たちは、風に身を任せて、わずかに傾きを作りながらこたえる。
その樹々が、少しだけ風に身を任せていることに、なぜか視線がとどまる。
樹々は、おそらく自然に対して、生を隅々まで応諾していた。
細長い緑の茎の曲線が、水滴を近寄せる。
水滴は、ただ一滴ながら、透明な世界を、生き物の曲線に沿って伝ってゆく。
皮膚を滑るように。
そのように、水滴は、皮肌の「内部」を開く。
流れる「時」は、一瞬から永い移りゆきへと世界を変える。
そして、気がつけば、白い和紙の前に、筆先が動いてゆく時間とともに居るのを、舞踏の微かな熱を感じながら確認する。
「関係」という見えない世界が、、墨に仮託して眼の前に見えている、
これは、線の浮上を可能にする墨色の物語というべきか?
「墨」(関係者をつなぐ橋)は見える・・・、「線」の根拠である「関係」は見えない。
私たちを取り巻く諸々の青や群青色や赤や黄色のイメージは、その背後に、見えない「関係」の存在を常に暗示することになっていたのだった。
「関係」の集積が背後にあるはずなのだ。
墨で描くということは、はるかに、自然現象にこの身が同化しているという意味をふくんでいる。
直線は天から、地球の中心に向かって降りてくる。
その身長ほどを切り取れば、雪の斜面を滑走してゆくスキーヤーの運動の軌跡が細部にわたって出現する。
勿論、この身長とは、手のうちに存る「筆」のことである。
墨の曲線は運動をつかさどる主体が姿を現した、その残影だ。( →③菊池春桂作品)
そこには、一個の身体と世界との関係の、その始まりと詳細のすべてがある。
運動を見事にとらえることは可能であるのか。
百メートルをスローモーションではしりぬけ、意識化された舞踏をのぼりつめることは可能であるのか。
自然の奥行きを捉えることは可能であるのか。
そして、その技は歌(詩)を歌い得るであろうか。