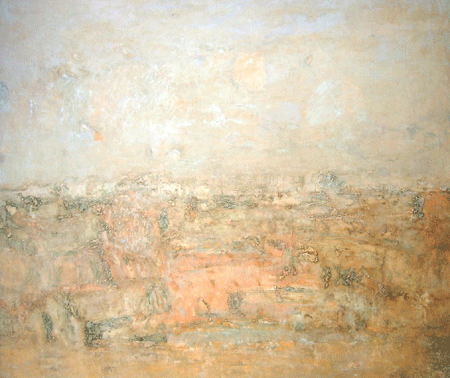石田さんの絵を観て考えたこと(1)
文 ことのは 宇田川 靖二
不二ひとつうずみのこして若葉かな (蕪村)
ここでは、不二とは「詩」であり、若葉とは「無限の諸関係」である。
*
●石田貞雄自選展
2012年6月 立川のたましんギャラリーにて、「石田貞雄自選展」があった。
会場の中央部分の部屋にはいると、石田さんの少し古い作品が並んでいて、それらが、かって私達が抱懐されていた時代へと、私達を誘っている。
石田さんは、1943年生まれであるから、絵を鑑賞する側では、戦後というほぼ半世紀にわたる同時代のイメージのなかで、それぞれ自分の世界に関係させつつ、ふりかえることができる。
私達が、ふりかえるというのは、今なお歩をやめていない、その動機を、対象を変え、形象をかえ、形式を変え、色彩を変えても、秘かに抱き続けている、そういう場所からふりかえるということである。
この部屋にある作品の落ち着いた色彩には、当時、世の中を覆っていた空気の、期待や不安や苦悩が滲みこんでいる。
多くの同時代人との、興奮の交わりは、すでにとおく過ぎ去ってはいるのだが、そして、すでに斃れた人々をも数えることはできるものの、念頭に去来するのは、常に次の短歌の情景である。
死者なれば 君らは若くふりそそぐ 時雨のごとき シュプレヒコール
(福島泰樹)
私達はまだかの時代の人々と、別離を果たし得たわけではない。
石田さんの昔のある絵画資料(個展の案内、於・紀伊國屋画廊)がある。(「流亡人」↑)
そこに、或る幻想の「家族」が描かれている。 (この個展の会期は1973年11月27日~12月3日)
いまは亡き坂崎乙郎(美術評論家)が短文を寄せている。
坂崎乙郎は、次のように書いている。
*
石田貞雄さんの「おど」は何年か前の自由美術展でいたく印象に残った。一家族の集団肖像画ともいうべき作品なのだが、そのおおどかで原初的な姿はすでに人間をこえて風景と呼んでもさしつかえなかった。
同時に、それは人間の孤独と愛の歌である。一家は文明という社会のなかで孤立し、しかも家族の各構成員の愛によって強靭であった。
石田さんはその後ずっとこの孤独と愛を描きつづけている。そして今度の大作に発展した。私たちはこれをまことの社会とみよう。というのはかれらは信頼によって支えられ、信頼ゆえに逞しいからだ。
かれらのスケールは大きい。一種の巨人主義である。日本にも巨人族がなかったわけではない。北斎の大観の。ただし、文明は私たちを矮小にし不信感を植えつける。石田さんはそれがたまらない。彼は英雄のいない英雄の時代を待望する。私たちの願いでもある。 <坂崎乙郎>
*
その大作を目の当りにしてみると、当時の空気はますます鮮明になる。
大きな社会変動の時代であった。
いま思えば、不思議な力の作用が働いていた時代であった。
ともに夢を見ることが可能であったからだ。
人々は突破口を求めて、信ずるに足るものを掘り起こそうとしていた。
あの深く重い奥行きのある色合いの1960年代から、そして70年代に至る美術は、色彩自体が、存在を抱え込んで苦闘していた。
●時代と絵の変貌
たましんギャラリーの中央の部屋から出ると、表面的には潮が引いていくような変化を感じる。
その理由は、私達の視界には、具体的な形象が消えているような絵がならんでいるからである。
「抽象絵画へ」というのではない。
「形が崩れるような視線」に作家の意識が転位したのだ、という印象を受ける。
しかし、同時代人としての私達には、容易にその変化に「了解」を与えられるであろう。
バブル経済へと向かっていった社会は、いつしか私達に、おおきな戸惑いを突き付けてきた。
気がつけば、街からシュプレヒコールは消えていた。
消すことのできないはずの、その声らは何処かに沈みこんでしまった。
風景が変わった。
同時に、テーマも、対象も、形象も、形式も、色彩も変わった。
かっては「労働者」という言葉ひとつで、人の群れが出来上がっていたが、その言葉も映像の中の花のような「観念色」の陰に、ほとんど捉えられなくなった。
こうして言葉も失ったとすれば、言葉の回復を射程においた、風景を取り戻さなければならない。
それは、かっての形や色を用いて作画をすれば、失われた言葉がたちあがってくるという単純な話ではない、そういう意味において、深刻なものである。
●「埋む風景」
石田さんは最近の作品のタイトルに、「埋む(うずむ)」という語をあてている。
作家の前には、先ず、「埋む」とは何であろうか?
何が「埋む(うずむ)」のであろうか? という問が横たわっている。
私達の前には、世界ほどの大きな風景の喪失がある。
美術の人々にとっては、存在の喪失であると表現してよい。
この「埋む」ということに、妥当な意味を与えなければならない。
これらの風景画には、いわゆる写真的な表現はとられていない。
しかし、対象として、常に風景を追いかけている。
画面に現れている様子は、あくまでも遠くの山々であり、近景にある丘の重複であり、そして、土地の起伏、太陽に面して作られた家々のかたまり、その配置のリズム。
屋根、壁、・・・の蠢動。
あるいは、全体から感じられる波のような鼓動。
主に、いわゆる造形力でこの作業が行われているはずだが、それにしても、形を崩したり、変形したり、色彩を平面化してみたり、調子を整えたり、そして、一枚の風景画として仕上げてゆく時に、この作家が見ているもの、即ち「埋む」とは何であろうか?
勿論、絵を構成する際の様々な要素といったものを見ているに違いないのだが、瓦礫の山とも見えるほど無秩序を思わせるこの作業が、決して破壊と混乱のようには感じられない。
風景の中にある、貫かれた秩序の意識を何らかの特性で、追いかけているにちがいない。
● もうひとつの存在としての「関係」
遠くに見える山は一個の大きなもの、のような存在である。
前方の丘もまたそうである。
起伏している土地、かたまりのような家々、屋根、壁、もまたそうである。
おそらく、そこにはもっと小さなもの、例えば、窓、そしてカーテン、花瓶の花、ボールペンや消しゴム・・・と、果てしなく続いてゆく小さな「もの」の存在が想像される。
翻れば、空の大きさもまた同様に画家達の意識に、まずは無限性をひらいている。
絵は、どのあたりかまで、その大きさを視覚的に追いかけており、どのあたりかで、とどまろうとしている。
だが、石田貞雄さんは、これらの「もの」たちの無限性の対極に存在する、もう一つの無限な存在を見ている。
もうひとつの無限な存在とは何か?
世界が静的である限りにおいては、それは、いくら探しても行き着くのは、「関係」でしかない。
もう一つの、無限な存在とは、「関係」ということばが指している「存在」である。
しかし、「関係」とは、一般には「存在」ということばでは呼ばれていない。
「関係」とは、山、丘、家、屋根、壁、窓、カーテン、花瓶の花、ボールペン、消しゴム・・・のような実体ではないからだ。
ものを支える「関係」とは「ものの影」のような在り方をしていて、「存在」としては常に失念され、無視されている。
● 「関係概念」で「関係」を捉える
それは、次のような事情が隠れているからだ。
私達は、山、丘、・・・家という「もの」は、実体概念を使って捉えている。
その結果、家や消しゴムは、「もの」という実体的な存在として認識されるのである。
だから、眼には見えず、掴めもしない「関係」という存在を捉えるには、「関係概念」を使って捉えるしか捉えることができないはずなのである。
そして、「関係概念」を使って「関係」を捉えると、「関係的存在」の世界が拓けてくる。
それは、「関係」というあり方をした「存在」だという意味である。
● 「関係的実体」と「実体的関係」というイメージ(認識)
だいたい、「もの」が「関係」なしに存在できることはあり得ない話だ。
逆もまた然りで「関係」は「複数のもの(こと)」なしには存在できない。
「もの」と「関係」とは、存在として不可分であり、一個の存在である、という他は無い。
丁寧にいえば、私達は、存在という「一個」を、「実体的関係」と「関係的実体」との二つのイメージで解釈している。
普通、それを「物質」や「もの」というように、「実体」だけ、切り離してイメージする(認識する)のであり、あるいは、「関係」だけ切り離してイメージしたり(認識したり)する。
● 「関係」という存在に「埋む風景」
森のような「もの」の群の影として、森のような「関係」の群が存在している。
石田貞雄さんには、風景において、恐らくその無限の「関係」が意識されているはずである。
空と雲、空と山、山と丘、丘と家、家と屋根、屋根と壁・・・。
そして、山と手前の土地、手前の土地とその家、家と家、家と空、屋根と屋根・・・、あるいは、三軒の家と山の稜線、別な五軒の家と土地の起伏との関係・・・、風景は、見ている位置が、数メートル移動しただけで、細部にわたってすべてが変化してしまう。
そこは、どんな小さな単位であろうと、「関係法則」が支配していて、実は無秩序であることはできない世界であり、ある位置から俯瞰した時、無秩序だと感じることがあるというだけのことだ。
風景=世界は、海のように「もの」が充満している。
同様に、海のように「諸関係」が充満している。
風景が埋む・・・。
山そのもの、丘そのもの、家そのもの・・・を見ようとするのではない。
山と丘とがその位置(=「関係」)を変える、丘と家とがさらにその位置を変える。
気がつけば家が動いて山との位置を変えている。
ここには、諸々の「関係」たちが、「もの」たちの背後に、無数に隠れている。
石田貞雄さんは、その「関係」を眼に見える場所へもちだそうとする欲求にあふれていて、見えざる「関係」の中に意識を投じる。
そこには、自己が画家であり続けることを意識している最中の、その作業が見える。
画面が相手をしているのは、極端に言えば「もの」ではない。
「関係」という、見えない「存在」の無限なのである。
こうして、私達は、人間の関係構造の海が、眼の前に「存在」として展開されていたのを知る。
風景は何に埋むのか?
無限の「諸関係」の「存在」に埋むのである。