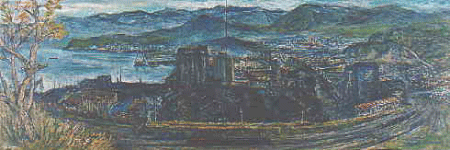佐藤 善勇さんの絵
文 ことのは 宇田川 靖二
1、小樽を描く作家
佐藤善勇さんの絵には、独特な直截性がある。
主に青が全体をおおっていて、世界から皮膚を通して、その冷気が伝わって来る。
私達もまた、同じ一つの世界の中に居る。
北海道・小樽の運河の、そのエリヤとその時代の強固な存在感が定着されている。
最近の、ヨーロッパの街を描いた作品にしても、何かを見落としていないか?何かを見逃していないか? と恐れでもするように、彼方まで投げられている視線が、景色の隅々にまで浸透しようとしている。
その過程で、作家佐藤善勇さんが何を見たのかを、言葉にするのはむつかしいことだが、どのような態度で対象に向かったのかは、その直截性ゆえに、はっきりと見てとれる。
2、探求の三様
これらの作品について、鑑賞者としての私の受容の仕方は、「存在とは何か?」という問に沿ったものだ。
この基本的な問を、人は、以下の三様の形で、直截に(無意識のうちにでも)発しているものだ。
以下のように、言い換えてもよい。
(a) 世界の全てを知りたい。
(b) 世界の根本を知りたい。
(c) この問を、自分が発している、そのことは何を意味しているのであろうか?
つまり、
(a)は、意識が極大に向かっている。
(b)は極小に向かっている。
そして(c)は自己に向かっている。
と言うことができる。
● (a)について
佐藤善勇さんの絵を観ながら、傾向の一つが浮かび上がるのに気付く。
それは、まず、大きな画面に向かった時の印象である。
人は子供の頃から、高い場所へ出かけて行って、遠くの山々を、あるいは自分が住んでいる町を、俯瞰しようとした。
そのように、「世界を見渡したい」と思ったのだ。
それは、自己を含む何事かを確認しようとして、であったのだろうか。
あるいは「世界を手に入れようとした」、と言ってよいのだろうか。
そして、眼の前の眺望に、実際、圧倒されたものだ。
その圧倒を、興奮しながら「世界を見た!」と、誰か他人に告げていた。
この世界の印象は、世界をトータルに把握しようとする自らの意志に、自らの情感が答えたのだ。
彼は、まさに、世界を眺望する、そのような、絵を描いている。
それは(a)の絵に代表される。
● (b)について
さらに、私達は、世界は、何でできているのか? と問う。
その根本は何なのか?
人の意識はそういう問に誘われている。
私達の意識は「世界の大きさへの俯瞰」とは逆方向に、「極小へ極小へ」と向かうことになる。
そして人は、その答を探し出す。
世界を構築している素材は、物質と精神である・・・、いや世界は原子というものでできている、いや素粒子で・・・あるいはさらに・・・。
そして、その構成単位をもって、自然科学者に代表されるように、世界を説明しようとするのだ。
そのために、人の探究心は、世界を構成している最小単位のイメージを、何か見出さずにはおかないのだ。
その最小単位で、世界を構成しなおそうとして、原子で「謎の微笑」を説明しようとしたり、それが不可能と知れば、さらに細部へと探求の方向を絞り込んだりする。
私は、佐藤善勇さんの多くの作品のうちに、謂わば「最小単位」と言えるものを探してみた。
そして、使用されている色彩に焦点をあててみた。
絵の全体をおおっている緑、青、そして赤・黄、白、黒、さらに茶、この七色が特に目立っている。
これらの絵の世界の、その色彩の最小単位は、この七色だといってもよいと思った。
様々に浮上している微妙な色彩は、これら七色が作用しあって出現する。
しかし、佐藤善勇さんは「その七色という元素を手にしさえすれば、絵(世界)を描くことができる」とは、勿論言っていない。
彼は、七色があれば、「謎の微笑」が説明できる、とまではさらさら語っていない。
元素(七色)を手にしていても、なお「根本」の世界にまで届かないからこそ、画面の色調が様々に変容するのだ。
「届かない・・・」という満たされない思いに似た変容である。
勿論、この七色の無限の組み合わせとその変容のうちに、世界の実相に通じる空間にいつか出会うことを願ってはいる。
だから、この七色は彼が描くことの出発点として選んだ、そういうものであろう。
● (c)について
目の前に広がる世界は、過酷でもある自然と向き合っていながら、人が住み、人が通い、人が言葉を交わしている、そういうところだ。
俯瞰と微細とに向かった佐藤善勇さんの眼は、どうしてもそこにいる人間というものに収斂されてくる。
人の住む家々は、外の冷気に閉じ込められて内側にこもる呻吟を漂わせている。
それは生活のうちに聴こえてくる声であり、心の明滅のように、寒暖をかかえながら静かに入り混じりつつ、変形する。
景色もろともに歪みをみせる。
「軋み」も聞こえてくる。
真っ直ぐに立とうとするが、さらにたわみの力が働いてくる。
そしてなお、面(おもて)を空に仰ごうとする。
働く人の姿が見られる。
連綿と続く明日の生活を感じさせる。
空や水の上を走る風の青、雪の白、それらが、情感を含んで土色と混濁し、人々の歴史の堆積を語る。
運河は、人々をその鏡の中に閉じ込めた、青く大きな水たまりなのであろうか。
「世界とは何であろうか」、人々の息吹きの無いところに、そのイメージを結ぶことはできない。
だから、同じように世界のうちに居住している自分の世界を観ることを通してしか、世界が現れることは無い。
これらの青い作品群こそが「世界」なのだ。
そのように、存在は語っている、と言ってよいのだろうと思う。