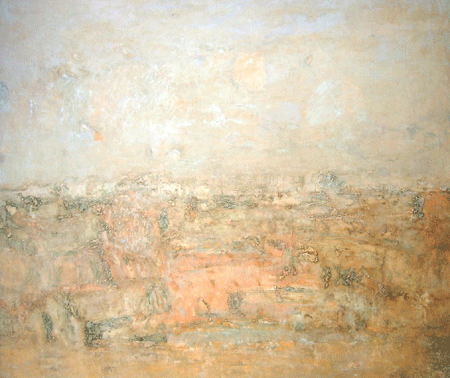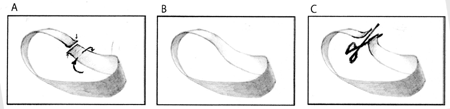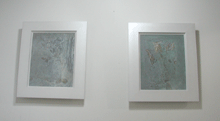~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石田さんの絵を観て考えたこと(1)
文 ことのは 宇田川 靖二
今、手元の、石田さんの昔のある絵画資料 (個展の案内、於・紀伊國屋画廊) をみている。(*「流亡人」↑)そこに、或る幻想の「家族」が描かれている。 (この個展の会期は1973年11月27日~12月3日)
当時、有名だった、今は亡き坂崎乙郎(美術評論家)が短文を寄せている。
坂崎乙郎は、次のように書いている。
****************************
石田貞雄さんの「おど」は何年か前の自由美術展でいたく印象に残った。一家族の集団肖像画ともいうべき作品なのだが、そのおおどかで原初的な姿はすでに人間をこえて風景と呼んでもさしつかえなかった。
同時に、それは人間の孤独と愛の歌である。一家は文明という社会のなかで孤立し、しかも家族の各構成員の愛によって強靭であった。
石田さんはその後ずっとこの孤独と愛を描きつづけている。そして今度の大作に発展した。
私たちはこれをまことの社会とみよう。というのはかれらは信頼によって支えられ、信頼ゆえに逞しいからだ。
かれらのスケールは大きい。一種の巨人主義である。日本にも巨人族がなかったわけではない。北斎の大観の。ただし、文明は私たちを矮小にし不信感を植えつける。石田さんはそれがたまらない。彼は英雄のいない英雄の時代を待望する。私たちの願いでもある。
<坂崎乙郎>
****************************
以上の文章は、当時の空気を実に彷彿とさせるものがある。
大きな社会変動の時代であったが、人々は突破口を求めて、信ずるに足るものを掘り起こそうとしていた。
もう40年近い年月がたっている。
ここで、私は、一枚の絵であることと、家族であること、の二つの世界を、私達の基礎的な「視線」(あるいは内的な視線)という観点から考えてみたい。
●
絵 と 家族 の双方について、共通に語り得る「視線」の問題は何であろうか?
さまざまな共通項が浮かび上がるのだが、基礎的・内的な視線だと思われる以下の二点に絞ってみよう。
① 「絵」と「家族」とをともに内的な視線からみると、それらは「転成(態)」(=超越態)である。
② 「転成(態)」には、私達のある視線が隠れている。
ここには難問が潜んでいると思われる。
日頃何でもなく行なっていることなのに、改めて考えてみると、うまくそのことの説明ができない、ちょうどそのような意味での難問である。
●
まず、「転成(態)=超越態」とはどういうことであろうか?
今、想像で、ある絵を分解して、数個の破片にし、ジグゾーパズル化してみよう。
この破片の集合は、そのままではただの破片の集合に過ぎないが、
うまく整えれば一枚の絵に、質的に「転成」する。
従って、絵は破片群を構成物として出来上がっている「統一体」である、ということができる。
この「統一体」というイメージは、その現象をまだ外側から眺めている場合である。
この際、破片は、「絵を形作る構成物」の比喩であるから、破片とは、作家の、力強い線や造形や色彩等、様々な材料や作業や思想感性の中身だと言ってよい。
しかし、「統一体」という言葉では、「転成」という「超越化する、内側のイメージ」は出現してこない。
その意味は、こうである。
絵とは、破片の位相からは、決して手の届かない場所へ転成してしまった、超越をはたした、そういう別の位相世界が出現した、ということである。
その転成を果たした絵は、「絵である他はない」。
もはや、破片という絵の構成者(物)は、絵という転成の位相からは、同世界に置かれることは拒否されている。
さらにその意味は、「転成(態)が本体なら、破片はその影に過ぎないもの」であり、
私達の日常が、「影など無視している」のと同様に、私達にとって、「事物は、影はなくても、本体のみで完結している」ということである。
この、絵とその内実を支える破片との関係には、特に気をつけなければならない。
絵は破片を内包するが、それは絵にとって、「影」のような存在として排除されていて、絵「本体」はあくまでも一個の存在として、一者としてそこに存る。
それは、もはや破片(影)の統一物だと外側から眺めて済むような世界ではない。
老若男女の誰もが、石田貞雄さんの「流亡人」をみ観れば、絵そのもの(本体)の印象から、「逞しい・・・」「かれらのスケールは大きい。・・・」と、先ず感想をもらすであろう。
このように、絵を観る人に、絵そのものから、えも言われぬ「影の予感」が漂ってはくるのだが、「影」は「本体」に、何となく魅力を放っていたり、怪しさを醸し出したり・・・
といったことの原因世界である、とは言えるのだが。
同様に、「家族」を考えてみよう。
私は、一個の人間である。そして、一人の男(性)である。
そして、妻と子と、計三人で、家族をつくり、それぞれは同じく家族の構成員である、と想像しよう。
「家族」は、個人の集合であり、外側からみれば、その統一体である。
そして、「家族」は、内側から眺めれば、転成態=超越態であって、(一枚の「絵」が「本体そのもの」であるように)一個の位相世界が出現しているのである。
もはや、「家族」の位相からは、個は「影」なのだ、として拒否されてしまっている。
この「転成=超越」を果たした「家族」の位相というのは、構成員である私が、「夫や父」であるということである。
だから、一個人とか一人の男というイメージとしては、「家族」の位相からは拒否されている、と言える。
要するに、家族を、私の内側世界から見れば、以下のような具合である。
私達は、そもそも「子」という「家族」構成員として生まれて来るのであり、一個の「男」あるいは「女」という「性の位相」にある存在として生まれて来るのではない。
家族に子供が生まれた時、「抱懐する存在=抱懐される存在」即ち「愛し=愛される存在」、そういうものとして生まれてくるのであり、そういう意味での「長男」とか「長女」とか、家族の「(男の)子」「(女の)子」が生まれたのであり、「男性・女性」が生まれたのではない。
また、一個の人間として生まれてくるのでもない。
男(女)として生まれてくるとか、一個の人間として生まれてくるとか、そういうイメージは、私たちが成長した後、客観性を認識(幻想)するようになってから訪れてくるものなのだ。
私達が体験して来た(内側からの視線の)実際は、客観性の視線(外側の視線)より「以前」から始まる。
一個の「男(性)」や「女(性)」という「非家族的位相」世界は、「家族」の外から、家族内部の思春期の「子」に対して、或る「違和感」をもって、家族の内側に初めて侵入してくるのである。
それまで「子」であった存在は、或る時、「おまえは男なのだ」(あるいは女なのだ)と、「家族もよいが、おまえはもっと別な意味で深い位相に存る存在なのだ」と
「告げら知らされる」のである。
通常は、そうして「子」供は、新たな位相の、新たな差異がもたらしてくる違和感から、「家族」の外へと弾き出され、独立(自立)してゆくことになる。
それが、おのずから他人(他の家族からの独立者)と家族の外の世界で交わることになり、従って社会は拡大し、多様なものに発展してくるのである。
これが、人の内側から見た私達の成長のプロセスである。
成人としての「父母」は、このプロセスを、既に体験済みの認識として持っている。
だから、家族の位相に存りながら、同時に家族の存在とは別の位相である、「男性・女性」でもあり、「家族としての父母」と、「性としての男女」という、二つの位相の「違和」を自己の内にかかえていることになる。
さらに又、一個の人間でもあるという意識を同時にかかえている。
人が一個の個体である、ということから、私達は初めから「孤独」ということが問題になっている。
従って、先ず、家族における(家族的抱懐からの)孤独、そして思春期からは、性における(性的抱懐からの)孤独、そして社会に出てからは社会における(社会的抱懐からの)孤独、そして、一個の人間としての(謂わば類的存在という抱懐からの)孤独、そういう「位相の異なる孤独ら」との出会いが、からまりながら私達を襲うのである。
この家族を、石田貞雄さんの「流亡人」においてみると、このような孤独の場所から照射されているのがわかる。
その家族は、外の世界に対して、頑固な主体性の根拠として現れてきている。
また、「巨人族」といったイメージからも、「族」の共同性の、その存在感が外の世界に対して強く主張されている。
結局、制作過程での石田貞雄さんの個としての営みが、「自己の根拠」を作品の土台に据えようという、
強い自覚に支えられているのがわかる。
●
さて、改めて考えてみると、外側から見れば、「統一体」であり、内側から見れば、「転成(超越)態」であるという現象は、いたるところで見られる、というより、私達の生活世界が、この「転成(超越)態」の連鎖で出来上がっているのである。
生まれた時から、生活に不可欠な水とは、水以外のものではない。
水素原子と酸素原子が集まって水という「転成(態)」が作られているのだが、水は既に原子レベルの位相を拒否して「水」以外のものではないことを主張している。
また、大半の「水」とその他の物質が集合して、物質は「生命」という位相に転成(超越)する。
個人、家族、社会、そして勿論、国民を集合させている「国家」もまた転成(超越)を果たした存在である。
国家の構成者は個人の群であり、家族の群であったりするが、位相の違いという意味では、国家は、一個人や一家族が同一地平にて手の届くという位相世界ではない。
これらの基礎に存るものは、私達の視線の問題である。
●
さて、ここでいう絵や家族が「転成・超越態」であるということは、外側から見ているのと違って、内側の視線で見ているということなのだが、それはどのような構造なのであろうか?
「転成(態)=超越(態)」が、外側から見た時は、ジグゾーパズルの破片をかかえた統一物である、ということ、この外側からの視線の話をとりあえず脇において、
内側から見て、構成者を「影」として拒否し、影を排除した一個の存在であること、そういう内側からの視線はどんな構造をしているのであろうか?
「絵」が「絵」の位相以外の存在ではなく、「家族」が、「家族」の位相以外の存在ではない、ということは、「絵」や「家族」はいかなる構造をもった視線で眺められているのであろうか?
ここからは、第二番目の問題、「視線の難問が潜んでいる」という角度からの話に移ろう。
それは、私達の視線が内包している構造の話なのであるが、以下のとおり、変化球を投げて考えてみる。
●
三つの視線(ABC)
「メビウスの帯=輪」というのがある。その「作り方」と「ほどき方」は以下「ABC」の図のようなものだ。
この不思議な輪を、「メビウスの帯」とか「メビウスの輪」といっている。
不思議な絵を描くエッシャーという画家にもこれを扱った絵があるのはよく知られている。
先の、ジグゾーパズルの「転成」(=超越)の例に沿って、この「ABC」について語ってみよう。
すると、以下のようになる。
ベルトがある。その両端を糊づけするのだが、その時、一方の端を180度ひっくりかえす。(→A)
すると、B図のように輪ができる。(=メビウスの輪)
次に、さらに、元の普通の輪に戻そうとすれば、Bにハサミを入れればよい。
以上の例で、ベルトの表裏二面が存在するのは、AとCである。
Bでは表裏が消えて、不思議なことだが、一面しか現象していない。
・A→ これは表裏という二者(パズルの破片)が、一者に転成しようとしている状況にある。〔 転成化=超越化〕
・B→ これは帯の表裏が消えて一者に転成したのであるから完成したパズルの絵そのものである。〔転成態=超越態〕
・C→ これはパズルの絵をばらして、二者(複数の)破片にもどした状態である。〔(転成・超越態の)解体化〕
家族を例にとると、以下のようになる。
・A→ これは、男女が婚姻を結びつつある状態で、家族を作りつつあるが、まだ家族に転成していない。
・B→ これは、婚姻後の、もう出来上がった家族の状況を意味している。
男女は、ここでは父母であり、子供は家族の一員である子であり、
いまだ男性(女性)に成長してはいない。家族内の男の子、女の子である。
・C→ これは、家族を作っている実体は何か? どんなジグゾーパズルの破片群でできているのか?
と家族を分析したりしているような視線を意味している。
石田貞雄さんの作画としては以下のようになる。
・A→ これは、絵を仕上げつつある、作画の途中の視線である。
・B→ これは、「流亡人」と題された、絵の完成態を観ている視線である。
・C→ これは、坂崎乙郎がその絵の分析をして、その絵の構成要素(複数)を探している視線等である。
●
ここは、坂崎乙郎の文章で、もう少し詳しくみておこう。
「・・・風景と呼んでさしつかえなかった。」というのは、「C→A→B」という視線のプロセスだと言ってよい。
なぜなら、「流亡人」を観て、坂崎乙郎が分析し、想像した(作った)イメージ(風景)の吐露であるからだ。
「同時に、それは人間の孤独と愛の歌である。・・・愛によって強靭であった。」というのも「C→A→B」。
なぜならの「流亡人」の構成内容(破片)をこのように分析し、そして「孤独・愛・強靭」というイメージを提出しているからだ。
「彼らのスケールは大きい。」この部分は、人が夕焼けをみて感じたままの印象をストレートに語っているようなケースであろう「B」。
詳細を考えれば、「ABC」の「いずれの視線のプロセスもどこかで経てきた」時間の体験がある、と考えられよう。
「文明は私たちを矮小にし不信感を植えつける。石田さんはそれがたまらない。」というのも、坂崎乙郎の分析・構成・イメージ結晶の吐露、という「C→A→B」のプロセスがあろう。
●
私達が、日常において、夕焼けの美しさに感動した時、その感動は、老若男女の感動である。
それは、「B」の視線の世界で起きているのだ。
(「B」は、「一切の破片群をただ影としてのみ内包している。)
およそ、私たちは、先ずは、このような「B」の生活世界(転成態=超越態)に囲まれている。
だが、そこから、画家や自然科学者は、さらに夕焼けについて、「C」へと分析の視線へ入り、そして、「A」へと新しいイメージを構築しようとして、研究室やキャンバスの前で苦闘する。
そうして、石田貞雄さんの「流亡人 B」が出来上がってくるのだ。
従って、画家達は、美術の専門家達や思考の専門家達だけにではなく、老若男女に広く親しまれる(夕焼けのような)作品「B」を描きたいと望んでいるものだ。
●
人間のボディーという一個の存在「B」は、「C」的な視線で考えてしまえば、物質と精神の、二つの世界でできている、という考え方にもなる。
「分離できない一個のボディー」を二つの世界でできていると仮定して、「分離可能だ」とした虚構を眺めているのだから、それでは、人は「仮定」とか「虚構」の世界に住んでいる、ということになる。
人々全員が、同じように考えてしまえば、その「分離可能だとの仮定=虚構」は人々全員にとっては真実となってくる。
だから人は、謂わば、現実に「仮定=虚構を生きたがっている」「仮定=虚構を生きている」ということができよう。
そして、その仮定=虚構の内で、人は全員、「自己とは、物質の方ではなく、精神の方だ」と考えたがっている。
さらに、この「精神」とは何であろうか?
2010年12月3日
石田貞雄さんの絵を観て考えたこと (2)
● 埋む(うずむ)とは何か?
今年の1月、石田貞雄さんの個展があった。
15点ほどの油彩画で、どれもみな「埋む風景」という題名がついている。
従って、「風景画」というふうにくくってみるのだが、それにしても「埋む(うずむ)」とはどういうことだろうか?
この「埋む」ということに、妥当な意味を与えなければならない。
これらの風景画には、いわゆる写真的な表現はとられていない。
しかし、対象として、常に風景を追いかけている。
画面に表れている様子は、あくまでも遠くの山々であり、近景にある丘の重複であり、そして、土地の起伏、太陽に面して作られた家々のかたまり、その配置のリズム。
屋根、壁、・・・の蠢動。
あるいは、全体から感じられる波のような鼓動。
主に、いわゆる造形力でこの作業が行われているはずだが、それにしても、形を崩したり、変形したり、色彩を平面化してみたり、調子を整えたり、そして、一枚の風景画として仕上げてゆく時に、この作家が見ているもの、即ち「埋む」とは何であろうか?
勿論、絵を構成する際の様々な要素といったものを見ているに違いないのだが、瓦礫の山とも見えるほど無秩序を思わせるこの作業が、決して破壊と混乱のようには感じられない。
風景の中にある、貫かれた秩序の意識を何らかの特性で、追いかけているにちがいない。
● もうひとつの存在としての「関係」
遠くに見える山は一個の大きなもの、のような存在である。
前方の丘もまたそうである。
起伏している土地、かたまりのような家々、
屋根、壁、もまたそうである。
おそらく、そこにはもっと小さなもの、例えば、窓、そしてカーテン、花瓶の花、ボールペンや消しゴム・・・と、果てしなく続いてゆく小さな「もの」の存在が想像される。
翻れば、空の大きさもまた同様に画家達の意識に、まずは無限性をひらいている。
絵は、どのあたりかまで、その大きさを視覚的に追いかけており、どのあたりかまでで止まろうとしている。
だが、石田貞雄さんは、これらの「もの」たちの無限性の対極に存在する、もう一つの無限な存在を見ている。
もうひとつの無限な存在とは何か?
世界が静的である限りにおいては、それは、いくら探しても行き着くのは、「関係」でしかない。
もう一つの、無限な存在とは、「関係」ということばが指している「もの(こと)」である。
しかし、「関係」とは、一般には存在ということばでは呼ばれていない。
「関係」とは、山、丘、家、屋根、壁、窓、カーテン、花瓶の花、ボールペン、消しゴム・・・のような実体ではないからだ。
ものを支える「関係」とは「ものの影」のような在り方で、存在としては常に失念され、無視されていて、存在としては語られていない。
● 「関係概念」で「関係」を捉える
それは、次のような事情が隠れているからだ。
私達は、山、丘、・・・家という「もの」は、実体概念を使って捉えている。
その結果、家や消しゴムは、「もの」という実体的な存在として認識されるのである。
だから、眼には見えず、掴めもしない「関係」という存在を捉えるには、「関係概念」を使って捉えるしか捉えることができないはずなのである。
そして、「関係概念」を使って「関係」を捉えると、「関係的存在」の世界が拓けてくる。
それは、「関係」というあり方をした「存在」だという意味である。
● 「関係的実体」と「実体的関係」というイメージ(認識)
だいたい、「もの」が「関係」なしに存在できることはあり得ない話だ。逆もまた然りで「関係」は「複数のもの(こと)」なしには存在できない。
「もの」と「関係」とは、存在として不可分であり、一個の存在である、という他は無い。
丁寧にいえば、私達は、存在という「一個」を、「実体的関係」と「関係的実体」との二つのイメージで解釈している。
普通、それを「物質」や「もの」というように、「実体」だけ、切り離してイメージする(認識する)のであり、あるいは、「関係」だけ切り離してイメージしたり(認識したり)する。
**「実体的関係」や「関係的実体」と解釈された(=イメージされた)一個の存在を、「一個」として捉えるには、「メビウスの輪の視線」を意識化しなければならない。 (→「石田貞雄さんの絵を観て考えたこと(1)」を参照)
その結果、「時間的存在」や「空間的存在」と同様「実体的存在」や「関係的存在」も、「一個の存在の部分面」を抽出した、謂わば「架空の存在概念」だという意味になる。
● 「関係」とう存在に「埋む風景」
森のような「もの」の群の影として、森のような「関係」の群が存在している。
石田貞雄さんには、風景において、恐らくその無限の「関係」が意識されているはずである。
空と雲、空と山、山と丘、丘と家、家と屋根、屋根と壁・・・。
そして、山と手前の土地、手前の土地とその家、家と家、家と空、屋根と屋根・・・、あるいは、三軒の家と山の稜線、別な五軒の家と土地の起伏との関係・・・、
風景は、見ている位置が、数メートル移動しただけで、細部にわたってすべてが変化してしまう。
そこは、どんな小さな単位であろうと、「関係法則」が支配していて、実は無秩序であることはできない世界であり、ある位置から俯瞰した時、無秩序だと感じることがあるというだけのことだ。
風景=世界は、海のように「もの」が充満している。
同様に、海のように「諸関係」が充満している。
風景が埋む・・・。
山そのもの、丘そのもの、家そのもの・・・を見ようとするのではない。
山と丘とがその位置(=「関係」)を変える、丘と家とがさらにその位置を変える。
気がつけば家が動いて山との位置を変えている。
ここには、諸々の「関係」たちが、「もの」たちの背後に、無数に隠れている。
石田貞雄さんは、その「関係」を眼に見える場所へもちだそうとする欲求にあふれていて、見えざる「関係」の中に意識を投じる。
そこには、自己が画家であることを意識している最中の、その作業が見える。
画面が相手をしているのは、極端に言えば「もの」ではない。
「関係」という、見えない存在の無限なのである。
風景は何に埋むのか?
無限の「諸関係」の「存在」に埋むのである。
2011年5月