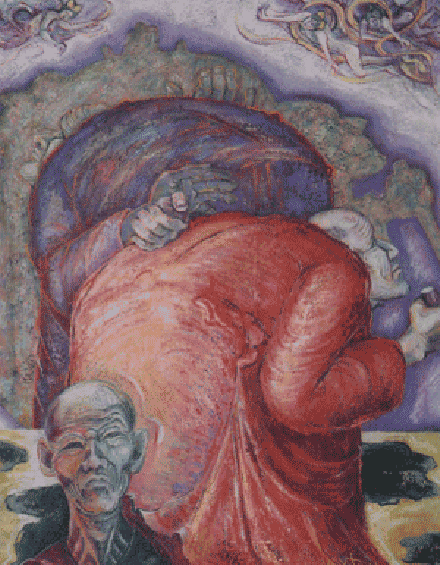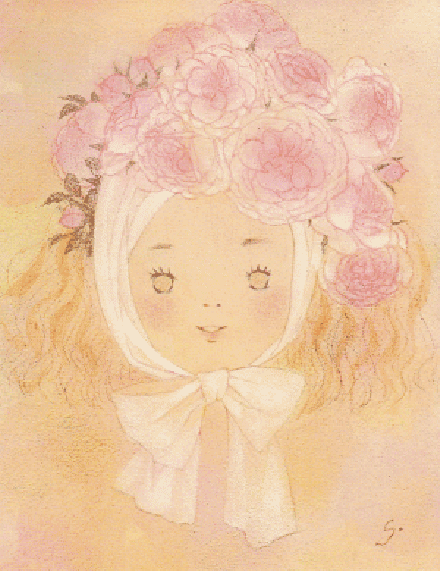内山清登
内山清登さんと関戸さやかさんの絵
文 ことのは 宇田川 靖二
空の青に眼をやりながら、近所の公園にきた。
落葉は、小道にしずかに重なっているだけで、かすかな音がきこえるものだ。
秋風が気持ちよくすぎていった。
シーソーに乗っている人がいる。
ゆるやかな音をたてる。
語っているのは、人なのではなく恐らくシーソーの方である。
乗っているのは老人だと気づいた時から、彼が何かの影をすこし背負っているように私には思えた。
老いと相反するバネのようなものがどこからか空気とともに伝わってきた。
老人が昔過ごしてきた時間に相違ないのだから、それも不思議ではないが、今現在の姿から生起してくるようにも思われる。
シーソーの反対側に乗っているのは若い婦人なのだと考えた。
小さな子供をかかえている。
シーソーから落ちてしまわないか、とも思ったが、絵の中で風が髪をかすかに揺らしている、そこへ注意が動いてしまった。
シーソーの左右に居る二人は、今年の春、私のギャラリーを訪れた。
同じ日のことではなかったし、それぞれ面識はないはずだ。
老人と若い婦人だということが、先ずはここで二人を結び付けている理由である。
もちろん、祖父、娘、孫の三人がある意味で同じ時を過ごしている、また別の意味で異なった時をそれぞれにすごしている、と考えても特に差し支えはない。
老画家は、人生の「結論」という最後の魅力を制作しようとしているかのように、老人の世界に集中して油彩画を描いている。
若い婦人は、日本画の道を歩いている。
我が子のうちに究極の表情を見出そうとしながら、日常の絵画言語の内部で、しかも初期人生の視覚言語を選んで、その内部で描いている。
それぞれの意味で、一点に向かっていると言い得る。
老人の画風は表現主義的で激しい。
筆致は奔っている。
過ぎ来し時間を奔ってきたのだから、というのは少しの理由でしかない。
実は老いゆえの、充実した勢いが、表現上の時間を奔らせているのである。
若い女流画家は、老いに向かう心性には無縁のようだ。
作画中の視界においては、人生の中間地点ですらまだイメージされていない。
ひたすら見詰めることに集中して、自然時間から遠く浮遊する。
奔れば世界が応答する、その最中にいるように意識はまっすぐである。
老画家もかってそのような時間を過ごしたことであろう。
また、秋風がとおり過ぎて行った。
私はどこにいるのだろうか?
恐らく、シーソーの中ほどの、支点という場所にいて、左右が交互にゆっくり上下するのを、感じるように眺めているのであろう。
なぜなら、老画家を見る時、若い女流画家の余韻が漂い、逆に、若い女流画家を見る時、老画家の姿が霞の中に浮かんでくるような気がする。
婦人の方が自然の色彩を純化したいと、思えば、老画家がその純化された絵の具で、自然の中にまだ隠れこんでいる色彩に還りたいと思う。
「抽象化したい・・・」
「いや、具象化したい・・・」
「天上へ・・・」
「いや、下降しよう・・・」
「過去をリセットして現在から始めよう。いったん過去を断ち切ろう・・・」
「いや、過去の集約が現在だ。みな宿命のようにいずれこの場所にくるはずだ・・・。過去とは何だろうか?」
双方は、基底において、実はお互いを無視するわけにはいかないことを感じているようでもある。
それはシーソーにのっているからだ。
シーソーの左右はゆっくり上下の運動を続ける。
秋の公園は、二つの存在が引き合い、また反発しあって、静かながら嵐をはらんでいる。
いや・・・、嵐の中に静けさがある。
私はどこにいるのだろうか。
恐らく「対」を観ているという支点の場所に呆然と立ち続けているのだ。
「対」の両者は対極にありながら、お互いに或る関係を保ち続けている。
そして、作家たちは、一方の極に集約する仕事を、分業しつつ担っている。
作家は可能性を自由に選択するし、またそれが可能だからだ。
観る側の私達は、双方の極を切り離し得る場所にはいない。
私達は落葉の様を追いかけるように、右に往き、左に還る・・・。
内山清登さんと関戸さやかさんの二人の絵の景色はかくも異なるのだが、私(達)は切り離せない相互関係の存在を感じながら、公園から立ち去ることができない。
公園のシーソーは、何事かが始まる場所だという直感があるからである。