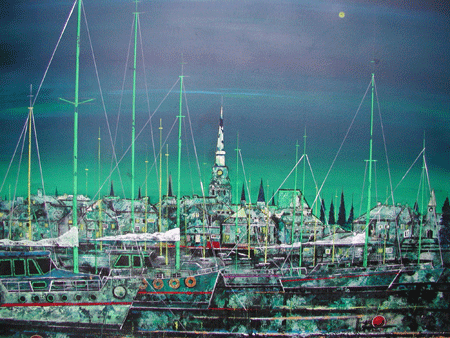遠竹弘幸さんの絵
文 ことのは 宇田川 靖二
1、画面上の「黒い帯」
気になっていた絵がある。
遠竹弘幸さんの、「黒い帯」のような直線が縦・横・斜めに幾本かひかれている油彩画である。
シャープさが十分伝わるような勢いを敢えてつくっている。
それらの多くは風景画である。
その風景というのは、どこか土からやってきたかのような黄土色や茶色で、その諧調を変容させつつ描かれている。
そこに、黒い絵の具の帯が、意志をもってひかれているのである。
彼は、ながい間この黒く力強い帯(or線)にこだわっているようなのだが、その黒い帯のイメージに何を託そうとしたのだろうか?
あるいは単に、気分ということではないとしたら、作品を観る側の、私(達)にとって、黒い帯はどのような意味になり得るのだろうか。
2、網膜剥離という視界・視線
昨年の夏、私は左眼の網膜剥離の手術を受けた。
剥離の経過は、まず左眼の、右下端に視界が隠れてしまう部分が現れた。
それは光を吸いこんで橙色をしていた。
その影は、平面的であったから、何となく聞き及んでいた網膜の剥離現象だな、という予感がした。
急いで医者にかかったところ、「すぐに手術が必要だ、大きな病院を紹介する」ということであった。
手術を受けるまでの数日の間に、その影は、少しづつ大きく上方に拡がってきた。
穏やかな色合いではあったのだが、視界を妨げるものが徐々に迫ってくる不気味さがあった。
具体的に何に迫ってくるのかというと、私の眼の焦点に向かってそれは近づいてくるのである。
「影がつくる塀」の上から、外の風景を覗き観ることができている間はよかったのだが、その「影の塀」はさらに高くせりあがってきて、ついに私の眼の焦点を越えた。
その時点になると、見たいものを見ようとしても、常時、「影の塀」が邪魔をしてしまう。
見たいと思ったものの、その周辺の部分が「影の塀」の上方に、視界の端として感じられるだけになった。
眼の焦点を、上方に向ければ、「影の塀」のもいっしょに上方に移動してきてしまう。
見ようとしている私の眼の焦点は、常に「影の塀」よりも下に位置する他はないことになってしまったのである。
この「影の塀」は、その塀の向こう側からの外の光を受けているから、暗いわけではないの
だが、
「見えない」という事実から、私には闇という印象をもって実感された。
私は、この事態を、次のように解釈した。
世界は「影の塀」の向こうに存るのだが、決してその世界を見ることができない・・・。
3、世界は網膜剥離現象の内部にある
私達が「世界を捉えたい」と思うのは、そこに未だ見えていないものの存在を感じるからである。
見えない・・・、という苛立ちや感慨は、先ずは作家達には一般的な前提なのだといわなければならない。
そして、「見えた!」という気持ちをもつことができたとしても、さらに、人々にそのことを告げて、確認し合わなければならない。本当のところは誰も知らないからである。
「ほら、君たちにもみえるであろう?!」という提出に応じて、
「なるほど、私たちにもよくみえる・・・」という同意が返ってこなければ、私たちは了解にはいたらない。
絵もまた、人々に語りかける言葉のようなものであり、
絵は、人々との確認や合意の瞬間を待っているものだ。
古来、作は、長品とい間その瞬間を待ち続けるような性格のものとして提出されている。
観る側もまた、その瞬間を求めて行程を旅するのだ。
見えることを妨げるもの、それはすでに風景の何気ない姿のうちにそなわっている。
「黒い影=塀」は、当然のことを特に意識化するだけのものとして、私達の視界・視線に宿命のように現れるといってよいのだろう。
4、黒い帯は、風景に溶け込む
「黒い影=塀」は、「黒い帯」となって、対象を把握しようと見詰め続ける作家達の前に障害物としてその姿を現すのだが、日々見えている山や川や町の姿こそが、すでに「影の塀」として存在している、といってもよいのだろう。
わざわざ「黒い影」を観るまでもなく、すでに「もっと見えないものか・・・」と常に作家達は渇望しているからである。
それが宿命であるかのように生きてきたからである。
ここへきて、
その「黒い帯」は、一体何であろうか?
と、「黒い帯」そのものを問うにいたる場所、そういう地点が出現することになる。
それは、この「黒い帯」に視線が集中するようになることを意味している。
そのことは、日々見えている山や川や町の姿を見ながら、「何故に、私達には、直接世界が見えないのであろうか?」という問に、執拗に食い下がろうとしているのと同じことだ。
それは作家というものにとってはもはや特殊な心性なのではなく、不可欠なものなのだ。
私達は、こういう疑問と共に佇んでいる自分を発見する。
その発見の時から、「黒い帯」が、眼の前に見える風景と同じ位置(意味)になり、黒い帯は、風景に溶け込むことになる。
むしろ「黒い帯」は、風景に昔から馴染んでいるものにさえなるのだ。
そのような、網膜剥離の状態に私達の視線は、もともとから置かれていた。
このことは、見詰め続ける作家にとっては、強く、くりかえし意識化されなければならないこ
とだ。
「黒い帯」の「影の塀」は、遠竹さんの風景画の中に、必然性をもって、問題として登場するのだと言えると思う。