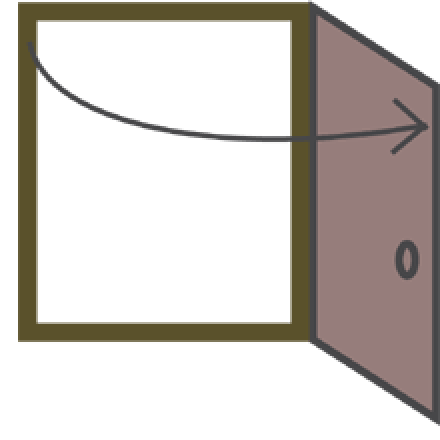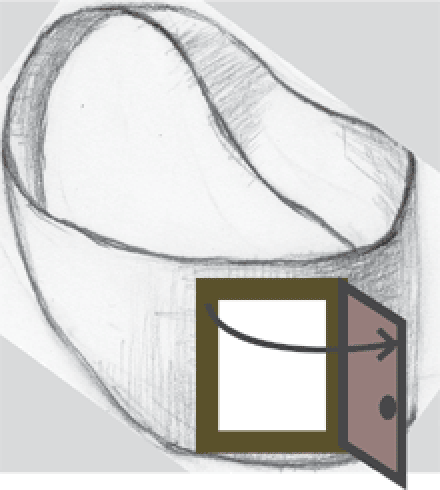「メビウスの環」を観る視線 について
文 ことのは 宇田川 靖二
1、
私は、浅い眠りから覚めて、やや空腹を覚え、向かい側の部屋に移動しようとした。
私の手が、その扉の蝶番を握り、その扉を開こうとした時、私はある不思議な感覚を予感した。
私は、ひと呼吸おいて、その扉を開けた。
その部屋には、私自身がいたのだ。
私が座っている机も、その上に、今飲んだ珈琲のカップも、読みかけの本も見える。
後方には、私の好きな絵も壁に掛かっているし、右脇の方には、昨日知人からもらったかすみ草がいっぱい花瓶にもってある。
電灯やカレンダーや古物が、眠気が残る部屋の空気を、吸い込んでいるようにしている、それまでもが、扉のこちら側の部屋と同じなのだ。
それが、鏡に映った映像ではないことがすぐにわかる。
私は、扉の向こう側の私と眼を合わせているわけではないし、鏡をみている場合とは、何となく諸々の角度が異なっている。
いや・・・もっと不思議な気持ちがする。
その扉のこちら側の部屋と、向こう側の部屋とが、「まったく同じ世界だ」という気がしてしかたがない。
むしろ、「双方が同じ世界だ」という確信のようなものが、深まってくる。
しばらく佇んで、部屋の中を眺め、扉のこちら側の部屋と向こう側の部屋とをくらべていたのだが、ついに眼をとじて眼以外の感覚を研ぎ澄ますようにして、両方の部屋を意識の世界で覗った。
そうして、「二つの部屋は、全く同じ世界だ」と結論せざるをえなかった。
しかし、現実にはあり得ないことだ、ということも、当然ながらわかっているのだ。
一体どういうことなのか? と、私はしばらく考え込んでしまった。
考えているうちに、ひょっとしてこの扉は「特別な建物」にとりついている扉なのかもしれないと思い、私は扉を遠くから見てみようとして、少しづつあとずさりを始めた。
視界の中に、その扉はだんだん小さくなってゆき、建物全体が少しづつ姿を現してきた。
それは、以前、エッシャーの絵でも見たことがある、「メビウスの環」という建物であった。
エッシャーの絵は、
「その帯の上を歩いている蟻が、果てしなく歩き続ける他はない」というイメージ内容を表現している作品であった。
それは、メビウスの環が、「表裏の二面が無く、一面でできている環(帯)である」からである。
扉は、表裏がない壁に取り付けられている。
だから、扉の向こう側とこちら側が、同一の世界だということになる、そういうわけであった。
2、
この「メビウスの環」の視線は、「事物には表裏がある」という(二元的な)観方を拒否するものだ。
それは、以下のように、(二元的な常識からはずれて)「一元論の視線」を強制してくる。
第一に、「一元論の視線」を強制してくるのであるから、私達は背後の世界(二元的な世界)を想像することは「できない相談だ」、ということを思い知らされる。
例えば、机を見ても、それが原子でできている、とか、「もっと、さらにもっと小さな単位のものが、本体だ」という、「とどまることを知らない」意識が、拒否される、そういう位相に私達が生きているということを告げられる。
別な例をあげれば、以下のような現象が思いあたる。
私達は、子供の時、家族の一員で過ごすのだが、
成長して一個の男性か女性になれば、それまでの存在(家族)である位相が、二元的な位相を意味してしまうことになるが故に、「性」か「家族」か、それらの一方は拒否されざるをえない。
個人が独立してゆく、という現象がこのようにして、一元的な視線によって自然に果たされてゆく。
(「二律背反」の理解には、一元的な視線が横たわっており、それが欠かせない、という構造になっている。)
第二に、私達が、生まれてすぐの、最初の赤児の視線というものを考えようとする時、それは、まだ事物の裏側を想像できない状態なのであるから、赤児の世界を考えようとすると、この「一元的な視線」のイメージが必要になるであろう。
第三に、私達が、抽象能力を駆使して、世界を様々に解釈したとしても、「世界とは、結局どんなものなのか?」という問に最終的に答えなければならない。
それには「メビウスの環の視線=一元的な視線」を意識化することによって、分解した諸要素を統一化(一元化)し、解釈前のもとの姿の場所に還らなければならない。
例えば、私達の前に、世界はあるけれども、私達は「時間と空間」という二要素の存在概念に分解して、世界を理解したりしている。
そのことは、解釈として間違いでもないし、日々そのように生活して不都合を私達は感じてはいない。
しかし、本当は「時間と空間」に世界が二分解などされることはない。
第四に、この視線は、「私達がつくるイメージは全て幻想である」ということを、私達に宣告する。
世界が、二元的で、「表裏がある」と思えるからこそ、私達は裏側のイメージをつくることができる。
扉の向こう側(裏)に誰か他人が居るのではないのか?と思ったりすることができる。
しかし、メビウスの環の視線には、向こう側(裏)はない。
裏が存在しないという前提の上での、裏側(扉の向こう側の部屋)の想像は、架空の世界だと言わなければならない。
この視線は、想像(イメージ作業)一般が基本的に「幻の姿として現れて来る」、ということを私達に通告してくるものである。
私達の、「真を掴もうとする」観念の、行く道は断たれている。
だから、私達はその意味で「帰路を強いられている」のである。
私が、その扉の向こう側の部屋に、窓から見えるかのように、「遠くの山々」や「婦人達」を見たとすれば、それは「何かしら、存在はしていても幻の姿を見せている」ということなのだ。
第五に、私達が「二元論の意識で」、
いくら「時間と空間を統一する・一元化する」と叫んでも、「言葉の上では、一元化することができる」と言っているにとどまる他はない。
本当はその「統一」の「一」を捉えることは「できてはいない」のだ、と言わなければならない。
この「一」という「一元的」なイメージは、「一元論の視線」で意識化しなければ、理解に達することはない、と考えることが要求されているはずである